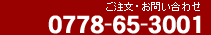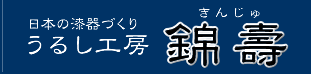 |
 |
|
|
山岸厚夫の漆の話今まで国内でも数回以上、NYでも3回 漆の話をして来ました。毎回録音しておけばよかったのですが全くそんなことは考えていなかったので、その時の思いつくまま話してきました。 【漆は漆の木から採れる樹液】 漆というのは漆の皮と幹の間から採れるのです。人が怪我をすると血液の中のキズを治す成分が出てきて固めキズを治して行きます。それと同じなんです 漆の木に最初 長さ2cmぐらいのキズをつけます、すると漆の木はそのキズを治そうとしてそのキズに治す成分が集まってきます、それが4日間かかるのです、その集まった頃に2cmのキズつけた位置から2cmほど上の所に3〜4cmぐらいのキズをつけて、そのキズから出てくる液体を採ります、この液体が漆です。 キズから出た時は乳白色をしていますが、空気に触れてすぐにビール瓶のような茶褐色の漆になります。 この生漆は木固めに使ったり下地に使ったりします この生漆は水分を多く含んでいるので、昔は太陽の光にあてて、今は室内で電灯の熱などで温めながら攪拌します、すると水分が蒸発することと、混ぜることにより品質が均一になり、漆の質が高まります。 このようにクロメ、ナヤシとよぶ工程をしたものが素黒目(すぐろめ)漆といいます。透きの素黒目と黒の素黒目があります この漆は中塗りとか蝋色仕上げをするときに塗ります、私のところではすべて素黒目漆を使用しています。 上塗り用には朱合(しゅうあい)漆と言って透明に近い漆とか、上塗り用の黒も塗立(ぬりたて-艶が高い)、艶消し黒、半艶消しなどあり、塗り師の要望で漆屋さんが色々ブレンド、工夫して作ります。 他にも梨地漆とか春慶漆とか色々ありますが、それは要望に応じて漆屋さんが作ります 【漆の性質とは】 漆は塗料など異なり、酸素を取り込み固まるのですが、水分をともなって酸素を吸うので湿度がないと漆は固まらないのです。ですからムロなどに入れる訳です。 【日本産の漆と中国産の漆】 数年前から大量に中国で日本の漆器のコピーと思われる商品が輸入されてバーゲン売り場や観光地などで売られているので、また最近、中国製造の食品の問題が大きいのでイメージはかなり悪くなったと思いますが、漆に関しては今、中国から輸入がストップしたら日本の漆器関係の製造会社は生産がストップしてしまうと思います 私どもでは今 10年計画で漆の木の植樹を計画しており、今年の冬までに漆の苗20本を畑に植えて、来年春には私の山に50〜100本植える予定です。 日本の漆と中国の漆の違いですが 【木製漆器は海外使用は大丈夫?】 私は100%大丈夫とは言えません、やはり国によっては非常に乾燥しているので木製の場合ヒビ割れが多いのも事実です。湿度の高い日本だから漆器は合っているのかもしれません 世界の博物館の漆器を修理した方に聞いても、個人的に聞いてもヒビ割れは多いです。 多くの奥様と話すると、木製より母体が樹脂製のものが安全という声が多いです。 |
| |
| |
|
有限会社 錦壽 (ゆうげんがいしゃ きんじゅ) 〒916-1232 福井県鯖江市寺中町21-2-1 TEL:0778-65-3001 FAX:0778-65-2490 店舗運営責任者:山岸厚夫 Copyright (C) 2004 KINJU. All Rights Reserved. |